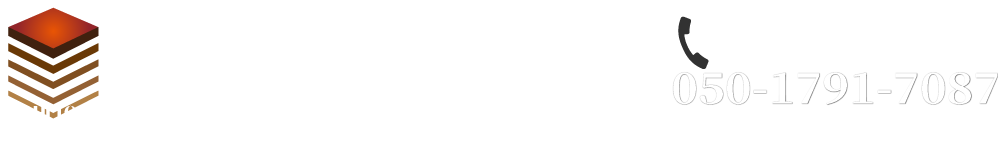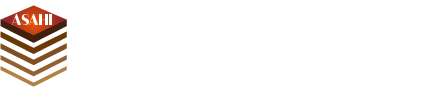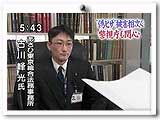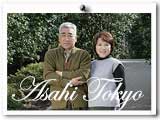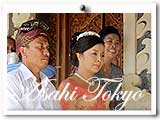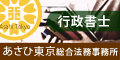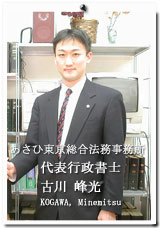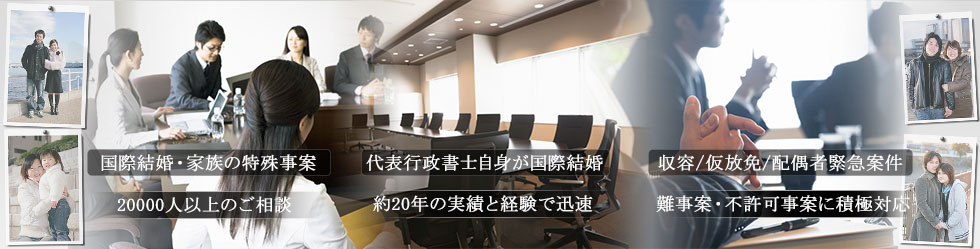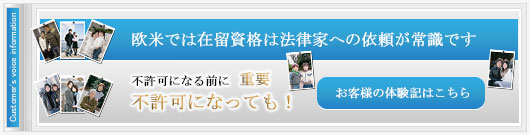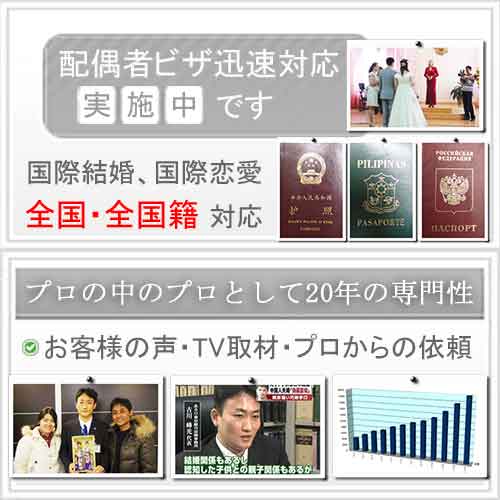ここでは研修ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。
‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの研修ビザのご説明‡
研修ビザに限らず、ビザの立証資料も地方局の具体的な場面において差異が生じることはありますし、一般的な資料は基本的には「必要条件」であって、「十分条件」では無いことに留意が必要です(入管や外務省の在外公館の場合、一般的な資料で足りるとは限らない。)。
- 研修ビザの法務Q&A
- Q1: 研修ビザとは、どのようなものですか?
- Q2: 研修ビザの要件(基準)は何でしょうか?
- Q3: 研修ビザでお金をもらっていいですか?
- Q4: 研修生(研修ビザでの在留者)に対して、研修手当て以外の賃金を支給した受け入れ機関はどうなりますか?
- Q5: 研修生にお小遣いを渡してもよいですか?
- Q6: 私は研修のビザで日本に来ていますが、外国人の友人から、働けるビザを持っている人は家族を呼べると聞きました。そこで、早速、本国の家族に電話して来日の準備を進めていますが、問題はないですよね?
- Q7: 研修ビザと似たものに「技能実習制度」というものがあると聞きました。それは何でしょうか?
- Q8: 「技能実習制度」を利用するにはどうすればよいですか?
- Q9: 研修生を受け入れる側としては、どのようなことに注意するべきでしょうか?
- Q10: 私は研修中ビザで来日中ですが、本国の父が危篤であるとの知らせが来ました。ビザの手続きはどうすればいいですか?
- Q11: 社内で「勉強」させる目的で短期滞在で招へいすることは可能ですか。
- Q12: 就労系の在留資格を有していた申請人が会社を辞め、いったん国籍国へ帰国し、その際、在留カード≒みなし再入国許可を残存させたままにして、その後、短期滞在の上陸目的で上陸申請した際、そのみなし再入国許可で再入国してしまったとき、その後に研修の認定申請をするとどうなりますか。
研修ビザの法務Q&A
研修ビザの在留資格も非常に「繊細」なものです。たとえば、申請人が以前、日本で就労系の在留資格を有して、就労していたとします。そこへその会社を辞め、いったん国籍国へ帰国したとします。ところが、その際、在留資格と再入国許可を残存させたままにして、その後、短期滞在の上陸目的で上陸申請した際、その再入国許可で再入国してしまったとします。さて、この人の研修の認定を交付するのが相当でしょうか。このページではその点も解説致します。
Q1: 研修ビザとは、どのようなものですか?
A1: 研修ビザとは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学及び就学の活動を除く。)、のためのビザないし在留資格です。
研修ビザも一般にはなじみのないビザでしょう。これは、元々は、国際間の技術移転を図ることを目的にしたビザです。
Q2: 研修ビザの要件(基準)は何でしょうか?
A2: 研修ビザは、以下が基準です。
一 申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
二 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること。
四 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技能等について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
五 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品の生産若しくは販売をする業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技能等を修得する研修(商品の生産をする業務に係るものにあっては、生産機器の操作に係る実習(商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所又は商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われるものを除く。)を含む。)をいう。第八号において同じ。)が含まれている場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が、我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が自ら実施する研修を受ける場合
ロ 申請人が独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修を受ける場合
ハ 申請人が独立行政法人国際協力機構の事業として行われる研修を受ける場合
ニ 申請人が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構技術センターの事業として行われる研修を受ける場合
ホ 申請人が国際機関の事業として行われる研修を受ける場合
ヘ イからニに掲げるもののほか、申請人が我が国の国、地方公共団体又は我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人若しくは独立行政法人の資金により主として運営される事業として行われる研修を受ける場合で受入れ機関が次のいずれにも該当するとき。
(1) 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関(以下この号及び次号において「あっせん機関」という。)が宿泊施設を確保していることを含む。)。
(2) 研修生用の研修施設を確保していること。
(3) 申請人の生活の指導を担当する職員を置いていること。
(4) 申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(あっせん機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
(5) 研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
ト 申請人が外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる機関の常勤の職員である場合で受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当するとき。
チ 申請人が外国の国又は地方公共団体の指名に基づき、我が国の国の援助及び指導を受けて行う研修を受ける場合で次のいずれにも該当するとき。
(1) 申請人が外国の住所を有する地域において技能等を広く普及する業務に従事していること。
(2) 受入れ機関がヘの(1)から(5)までのいずれにも該当すること。
六 受入れ機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
七 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から一年以上保存することとされていること。
八 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の四分の三以下であるとき又は次のいずれにも該当し、かつ、実務研修の時間が本邦において研修を受ける時間全体の五分の四以下であるときは、この限りでない。
イ 申請人が、本邦において当該申請に係る実務研修を四月以上行うことが予定されている場合
ロ 申請人が、過去六月以内に外国の公的機関又は教育機関が申請人の本邦において受けようとする研修に資する目的で本邦外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、一月以上の期間を有し、かつ、百六十時間以上の課程を有するもの(受入れ機関においてその内容が本邦における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合
Q3: 研修ビザでお金をもらっていいですか?
A3: 「報酬」をもらうことはできません。但し、渡航費、滞在費等はもらえます。たとえば、家賃等はかまいません。なお、もし滞在するのに必要な以上のお金を受け取っているときは、「資格外活動」となりますし、退去強制及び刑事罰の対象になります。
Q4: 研修生(研修ビザでの在留者)に対して、研修手当て以外の賃金を支給した受け入れ機関はどうなりますか?
A4: その場合、「不法就労助長罪」(法73条の2)に問われることがありますし、以後は不正行為を行った機関として研修生の受け入れが認容されないことになります。さらには、研修に限らず、あらゆる外国人の招聘に際して、不利に斟酌されます。
Q5: 研修生にお小遣いを渡してもよいですか?
A5: 食費、教材費、お小遣い程度はかまいませんが、名目いかんを問わず、就労の対価と認定されるときは違法ですのでご注意ください。それらの金額等は事前に十分調査されたほうがよいでしょう。
Q6: 私は研修のビザで日本に来ていますが、外国人の友人から、働けるビザを持っている人は家族を呼べると聞きました。そこで、早速、本国の家族に電話して来日の準備を進めていますが、問題はないですよね?
A6: 人文国際ビザや技術ビザでは家族滞在ビザで呼べますが、研修ビザでは呼べません。研修ビザも事実上は「働く」状態にはなるわけですが、あくまで「研修」であることから、家族は呼べないことになっているのです。但し、短期ビザで一時的に呼ぶことは可能です。
Q7: 研修ビザと似たものに「技能実習制度」というものがあると聞きました。それは何でしょうか?
A7: 研修生が研修を修了したあとに、就労することを認める制度です。
機械・電気関係、繊維関係、建設関係、等において認容されています。
Q8: 「技能実習制度」を利用するにはどうすればよいですか?
A8: 手続き的な要件としては、研修の終了前に、「研修」の在留資格から、「特定活動」の在留資格への在留資格変更許可申請が必要です。
Q9: 研修生を受け入れる側としては、どのようなことに注意するべきでしょうか?
A9: これは研修生に限りませんが、一般に外国人を受け入れるときは、まず、食事についてそれぞれの出身国の事情を考慮に入れる必要があります。また、アジア諸国出身の場合、日本の戦時中の話題に注意する必要があります。そして、直接の担当になる日本人従業員にはこうした留意点につき、周知徹底を行っておく必要があります。
さらに、外国人側に対しては、予め、日本の生活習慣について、十分な説明を行っておくべきです。たとえば、ゴミの捨て方、お風呂の入り方、クーラーの使い方、病気になったときの対応方法、などです。それから、研修生は労働力の代わりではないことに留意が必要です。
Q10: 私は研修中ビザで来日中ですが、本国の父が危篤であるとの知らせが来ました。ビザの手続きはどうすればいいですか?
A10: 受け入れ先の会社等に伝えて一時帰国の同意を得てください。そして、必ず、入管で再入国許可を申請してください。再入国許可を得ないで出国すると、今ある研修ビザは無効になります。
Q11: 社内で「勉強」させる目的で短期滞在で招へいすることは可能ですか。
A11:可能な場合はあります。但し、「勉強」させる目的での短期滞在と「研修」の在留資格の区別は非常に微妙な場合があります。
Q12: 就労系の在留資格を有していた申請人が会社を辞め、いったん国籍国へ帰国し、その際、在留カード≒みなし再入国許可を残存させたままにして、その後、短期滞在の上陸目的で上陸申請した際、そのみなし再入国許可で再入国してしまったとき、その後に研修の認定申請をするとどうなりますか。
A12:不交付になる例があります。なぜ、そうなのかですが、法は、適法性と妥当性を区別しますが、ここでは妥当性が問題だと解され、入管では、以前の在留の妥当性が、以後の在留の許否に影響するわけです。つまり「不当な在留」が以後の在留に影響するのです。「不当在留」とは興味深い言葉です。不法在留ないし不法滞在ならぬ、「不当在留」、「不当滞在」の問題、コンプライアンスの重要性が分かるというものです。類似の事例を挙げれば、研修先から逃走した場合、たとえ不法滞在ではなくとも、以後の在留に影響します(たとえば、日本人と婚姻した場合の日配の認定の拒否事由になり得る。)。
この設例のような「妥当性」が問題になる場面は、これに限らず、多々あるところですが、インターネット上の一般の方が書いた情報を見ると、適法性の問題と妥当性の問題が混同されている場合が多く、注意が必要です。
なお、上記の就労の再入国の事例では、実際には空港の入管の支局の現場の扱いとの絡みがあって、常に必ず認定を不交付にするのが相当とまでは言えないことにも留意が必要でしょう。